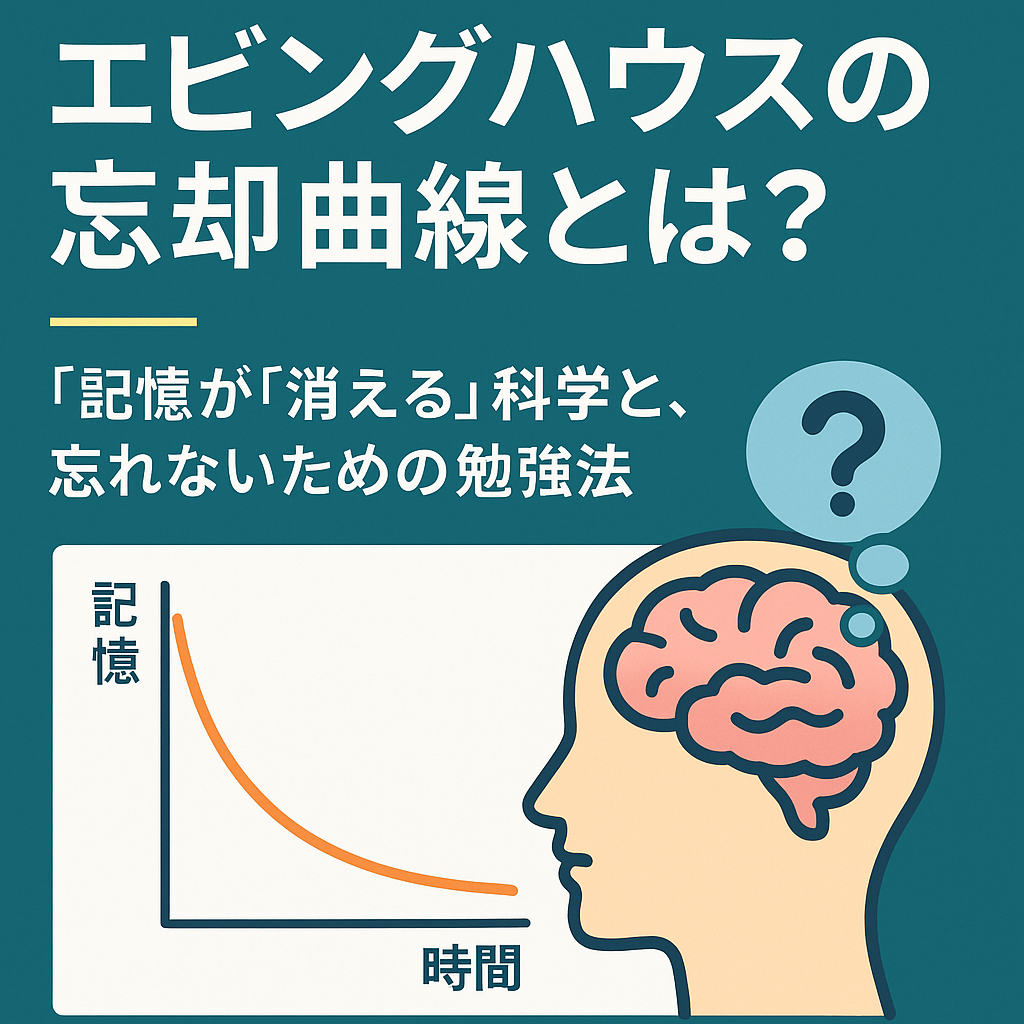「ものを持つこと=豊かさ」だった時代はもう終わりつつあります。今の日本でお金が貯まらない人の多くは、収入の額よりも「持ちすぎていること」でお金と時間と集中力を失っているんですよね。今日はそこをガッツリいきます。
昭和〜平成初期くらいまでは、ものを持っていることがその人の生活レベルや信用を映す時代でした。家電を揃える、車を持つ、マイホーム、ブランドバッグ……「持っている=生活が安定している」という分かりやすい図式があったからです。
ところが今は真逆です。
- サブスクで“使用権”だけあればいい
- ネットでほぼ何でも翌日届く
- デジタル化で「保存」より「アクセス」になった
- 賃貸でも十分・車はカーシェアでOK
- そもそもものを置くスペースを持つこと自体がコスト
つまり「持つことのメリット」より「持ち続けるコスト」のほうが大きくなった。ここに気づけないと、頑張って稼いでもなぜか貯まらないルートに自動で乗ってしまいます。
💸 1. ものは“買ったとき”より“持っているとき”にお金を奪う
多くの人が見落としている一番のポイントはこれです。
お金が出ていくのは購入時だけじゃない。
“所有している期間ずっと”コストが流れ続ける。
たとえば車。買った瞬間にお金が減るのは当然として、
- 駐車場代
- 保険
- 車検
- 税金
- メンテナンス
- 洗車
- そして「使ってないのに置いてある」というスペースコスト
が、乗らなくても発生します。実質“所有税”みたいなものです。
これは家電やアウトドア用品、服、趣味の道具、収納家具でも同じです。家に入った瞬間にコスト化する。しかも持ち物が増えると“それをしまっておくためのもの”まで必要になり、さらにコストが増える。
つまり
ものを増やす
→ 収納が要る
→ 広い家が要る
→ 家賃・ローンが上がる
→ 固定費が上がる
→ 貯蓄の余力が下がる
→ 将来の投資ができない
という 「持つインフレ」 が起きるんです。
📦 2. スペースコストを甘く見てると一生お金が残らない
前のあなたの記事でも少し触れていましたが、家って“何㎡借りるか・買うか”で毎月の固定費が決まります。つまり、
ものを1つ家に置く=そのぶんの家賃を毎月払ってる
ということでもあります。
たとえば1㎡あたり1,600円/月かかる地域に住んでいて、3㎡分の「使ってないけど置いてるだけのものスペース」があったら、それだけで
- 1,600円 × 3㎡ = 4,800円/月
- 年間 57,600円
- 10年で 57万6,000円
を“ものの居場所のためだけに”払ってるってことになります。こわくないですか。
しかもそれが「布団圧縮袋で小さくしてあるから大丈夫です」とかじゃないんですよ。スペースを占有している以上、コストは発生している。賃料・ローンだけじゃなくて、掃除の手間、探す時間、見た目のストレスも全部コストです。
⏱ 3. ものは「時間」も奪う。時間が減るとお金が貯まらない
“持つとお金が減る”という話をすると、「いや、置いてるだけならお金かからないでしょ」と言う人がいます。でもそこにはもうひとつ見えにくいコストがあります。それが 時間コスト です。
- 探す時間
- 手入れする時間
- 壊れたときに調べる時間
- 収納し直す時間
- 引っ越しのときに仕分けする時間
- メルカリに出すかどうか悩む時間
- 捨てるか迷う時間
ものが多いだけで、これが全部大きくなる。
で、この「時間を奪われる」のがなぜ貧乏に直結するかというと、 時間がないと単価の高いことに投資できないから です。
- 勉強する
- 副業をする
- キャリアアップのための読書をする
- 健康を保つために運動する
- 家計を見直す
- 投資を調べる
こういう「未来のお金を増やす行動」ってほぼ全部、まとまった時間を必要とします。でも家に帰って散らかったものを片付けて、出しっぱなしの書類を整えて、しまう場所のないコートをハンガーにかけて……とやってるうちに夜が終わる。
結果、「今月も勉強できなかった」「投資のことよくわからんからまた今度でいいや」で終わる。これはもう “ものが学習機会を奪ってる” と言っていいです。
🧠 4. ものが多い家ほど「買い足す発想」になる
これは行動経済学っぽい話ですが、ものを持っている人ほど「買ったら解決する」と考えがちです。
- キッチンがごちゃごちゃする → 収納ボックスを買おう
- 書類が散らかる → ファイルケースを買おう
- 洋服が多い → ハンガーラックを買おう
- 机にものが多い → サイドテーブルを買おう
でも本当は逆で、「足りない」のではなく「多すぎる」んですよね。
ところが、人間の脳は 「足す」ほうが「引く」より簡単 に感じるので、困ったらモノで解決しようとする。これが一度始まると、
ものが多い
→ 整理のためのものを買う
→ さらにものが増える
→ さらに収納が要る
→ さらに広い家が要る
という終わらない「増やすループ」に入ります。これはお金が残らない人の典型パターンです。
🧠 5. 「高いものを1つ」より「安いものを10回」のほうが貧乏になる
現代の貧乏って、ものすごく地味に進行します。高額な買い物より、安いものの回数 のほうがきいてくるんです。
- 1,200円の収納ボックス × 10回
- 990円のインテリア小物 × 毎月
- 2,000円の便利グッズ × 思いついたときにポチる
- 3,000円の服を「安いから」と毎月2着
これって1回1回は小さすぎて「節約できてる」とすら思ってるんですが、年間で見ると5〜10万円くらい平気で飛びます。しかも、それを収納するために家賃も上がってるので実質もっと高い。
つまり、
安いものは「お財布にはやさしい」けど「人生にはきつい」
ということです。これが「安く買ってるのにお金が貯まらない」の正体です。
📱 6. デジタルで代替できるのに“持ちたい”が止まらない
今は「持たなくていいもの」が爆増しています。
- 本 → 電子書籍
- CD → サブスク
- DVD → サブスク+配信
- 写真 → クラウド
- 書類 → PDF・Notion・クラウドストレージ
- メモ → メモアプリ
- 手帳 → カレンダー
にもかかわらず「やっぱり紙で持っておきたい」「棚に並んでると嬉しい」と、物理を2重で持ってしまう人がいます。もちろん“趣味として集める”ならそれでいいんです。でもそれが「安心のため」「捨てるのが怖いから」だとしたら、それはもう 心理的コストをお金で解決している 状態です。
そしてこの心理があると、こうなります。
- 保険を多めに入る(=安心のための支払い)
- サブスクを解約できない(=失う不安)
- 予備を買いすぎる(=不足不安)
- 家を広くしたくなる(=ものを捨てられないから)
結果、「不安を持っている人ほど、ものが増え、お金が減る」 というスパイラルになります。だからこそ、今の時代は「捨てられる人」のほうが貯まるんです。
🪤 7. マーケティングは「不安+収納」であなたを捕まえる
お店・EC・SNSがめちゃくちゃ上手いのはここです。現代のマーケティングは
「あなたの生活、ちょっと足りてないですよね?」
「これを“持てば”スッキリしますよ」
と“所有を正義にする文脈”で売ってきます。収納グッズ、便利家電、持ち物をカスタムする小さなパーツ、ハンガー、ケース、ボックス、トレー、カゴ、間仕切り、コレクション棚……。
でもこれって実は
ものを減らす → 不要
ものを持つ → 必要になる
という仕組みになっていて、根本的には「ものを減らさない限りずっと買い続ける」構造なんです。つまり “持つ派のお客さん”のほうがマーケ側からすると超おいしい。だからこそ「持たないでいいですよ」とは誰も言ってくれない。
ここに気づけるかどうかが、現代の家計ではめちゃくちゃ大きいです。
🧪 8. なぜ“持たない人”のほうが資産が増えやすいのか
逆に、ものを持たない人・持つものを決めている人は何にお金を回しているかというと、
- 金融資産(投資信託・株・ETF・NISA)
- 自分のスキル(語学・資格・プログラミング・発信力)
- 健康(ジム・食事・睡眠環境)
- 経験(旅行・人と会う・学びの場)
- 時短(家電・サービス・外注)
にお金を使っています。これらは「持ってるだけで価値が下がるもの」ではなく「使うほど将来のキャッシュフローがよくなるもの」です。つまり、キャッシュを“棚にしまう”のではなく“回るところに置いてる” んですね。
だから同じ年収でも、持たない人のほうが手元の資産は増えるし、将来の選択肢も広がります。逆に、持つ人はずっと今の生活を維持するためのコストを払い続けるので、働くのをやめられない。
🔍 9. 「ものが多い=思考が散る=仕事の質が下がる」
もうひとつ気づきにくいポイントを。
部屋が散らかっていると仕事の集中力が落ちる、というのは認知心理学でもわりと有名な話です。視界に入る情報が多いと脳のワーキングメモリがそっちに取られてしまって、本当に考えたいことに集中できなくなる。
するとどうなるか。
- 集中できないから仕事に時間がかかる
- 時間がかかるから残業になる
- 残業で疲れるから外食が増える
- 外食でお金が減るし健康も落ちる
- 健康が落ちるから医療費がかかる
- そして片付ける時間もなくなる → さらに散らかる
という、地味に強力な“家の散らかりスパイラル”に入っていきます。これは「ものを持つことが貧乏になる」というより「ものを持つことが貧乏になりやすい環境をつくる」といったほうが正確かもしれません。
🧹 10. 現代でお金を貯めたいなら「持ち方」を決める
ここまで読んで「じゃあ何も持つなってこと?」と思ったかもしれません。そうじゃないです。今の暮らしで大事なのは “何を持つかのルールを持つ” ことです。たとえばこんな感じ。
- “毎月お金を生まないもの”は基本増やさない 服・雑貨・収納・置き家具は優先度を下げる。
- “使う頻度が低いもの”は所有よりレンタル・シェア キャンプ・スーツケース・大きい家電・車はまず借りる。
- 家に入れる数と出す数を揃える 1つ買ったら1つ手放す。これだけでスペースは死なない。
- 家賃で管理できる量だけを持つ 収納を増やすために家賃を上げない。上げるときは収入アップとセット。
- 「所有したい」ではなく「アクセスしたいか」で考える 本当に“持ってないと嫌なもの”だけを買う。
この5つをやるだけで、ものを持つことが原因の“じわじわ貧乏”はかなり防げます。ポイントは「節約するぞ」と気合いを入れるんじゃなくて、家に入る入口で止める こと。買ってから後悔するより、最初から買わないほうが10倍ラクです。
✋ まとめ|“所有”より“軽さ”が価値になる時代
- 昔:持っていることに価値があった
- 今:持たないことに価値がある
このくらいパラダイムが変わっています。
ものを持つこと自体が悪いわけじゃない。でも、「持つときにかかるコスト」じゃなく「持ってる間じゅうかかるコスト」 を見ないと、気づいたら給料が全部“場所代・維持費・収納のための収納”に吸われます。
お金を増やすって、投資の勉強よりも、まずこの「減らさない設計」を作るほうが早いです。
だからこそ今の時代は、
何を持つかより、何を持たないか
を決めた人から、先にお金と時間が自由になっていきます。
 CobaruBlog《コバルブログ》
CobaruBlog《コバルブログ》