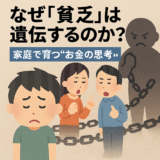こんにちは、COBARUです。
普通のサラリーマンとして働きながら、30代で資産2400万円を築きました。
もともと私は“節約マニア”でした。
スーパーのチラシを毎日チェックし、ポイント還元デーにまとめ買い、セールには真っ先に参戦。
「安い=正義」「安く買えばお得」と信じて疑わなかったのです。
しかし、資産が増えていく過程で、ある大きな気づきがありました。
「安さを追いかけている人ほど、お金が貯まらない」
一見お得に見えても、そこには見えないコストと心理の罠が潜んでいます。
この記事では、私自身の実体験と行動経済学の観点から、「安いから買う人が貯金できない本当の理由」を解説します。
🧠 「安いから買う」が危険な理由は“思考停止”
節約のつもりで「安いから買う」行動をしていると、実はお金の管理能力が低下していきます。
なぜなら、“安い”という言葉が判断基準を奪うからです。
本来なら「それが本当に必要か?」「将来の支出と比べてどうか?」と考えるべきところを、
「安い=買っていい」と脳が自動的に判断してしまう。
つまり、「安い」という言葉で考える力が止まるのです。
行動経済学で言うと、これは**「ヒューリスティック(直感的判断)」**という心理メカニズム。
忙しい現代人ほど、この“脳のショートカット”に頼って損をします。
🛒 ① 半額シールの魔力|「得した気分」が生む浪費
スーパーで半額シールを見ると、なぜかテンションが上がりますよね。
実際、私も昔は「今のうちに買わなきゃ!」と惣菜を大量にカゴへ。
しかし、その結果どうなったか。
-
食べきれずに残す
-
食べ過ぎて健康を損なう
-
翌朝「なんで買ったんだろう」と自己嫌悪
“安い”と感じる瞬間、人は冷静さを失います。
これは**「プロスペクト理論」**で説明できる現象。
人は「得をする喜び」よりも「損をしたくない恐怖」に強く反応します。
半額惣菜を買わないと「損した気分になる」──それが無駄遣いの正体です。
🍙 学び
「安い=得」ではなく、「使い切れる=得」と考える習慣を持つこと。
節約の本質は、値段ではなく“使い切る力”にあります。
🧴 ② 日用品を安いときにまとめ買いする人の盲点
「ティッシュも洗剤も安いときに買いだめしておけば安心」と思っていませんか?
実は、これも立派な浪費のひとつです。
ストックを家に置くということは、“家賃を払って保管している”のと同じ。
たとえば私の住む神奈川県では、1㎡あたりの家賃相場は約1,600円/月。
1㎡の収納スペースを1年間使えば約19,000円を“保管料”として支払っている計算になります。
しかも、ストックが多いと「まだあるし使っていいか」と消費量が自然に増える。
心理学ではこれを**「パーキンソンの法則」**と呼びます。
“モノがあると、それに合わせて行動量が増える”
つまり、「安いからまとめ買い」は一見合理的に見えて、実は浪費行動の温床なのです。
💡 節約のコツ
「買いだめ」ではなく「買い替え」。
在庫ゼロで不安になった瞬間が、真の“最安タイミング”です。
🛍️ ③ セール・福袋・キャンペーンの罠|脳が“買わされる”
セールやポイントキャンペーンに弱い人、いませんか?
私も昔は「今日だけ10%オフ!」の文字を見ると、理性が吹き飛びました。
でも、セールとはお店側の**“心理設計”**です。
行動経済学ではこれを「アンカリング効果」と呼びます。
「元値〇〇円 → セール価格〇〇円」と書かれていると、
本来の価格を基準に“安い”と錯覚してしまうのです。
さらに危険なのが、「一貫性の原理」。
「セール会場に来た自分」に一貫性を持たせるために、何かを買わないと落ち着かない。
“セールに来た=買うのが当然”という心理回路が働いてしまう。
結局、「安いから」という理由で買った物は、後悔の種になることが多いのです。
🧾 対策
-
欲しい物リストを事前に作る
-
予算を決めて行く
-
「セールがなければ買わないか?」を自問する
🧠 「安さ依存」が生む2つの心理的弊害
「安いから買う」人ほど、次の2つの心理に支配されます。
1. 損失回避バイアス
「今買わないと損するかも」という焦り。
でも、本当の損は“いらないものを買ってしまうこと”。
2. 所有効果(エンダウメント効果)
一度買ったものに価値を感じすぎて、
使っていなくても「もったいない」と捨てられない。
結果として、部屋も財布もどんどん窮屈になっていくのです。
🧩 お金が貯まる人の共通点は、「安さ」ではなく「納得感」で買い物をしていること。
「これが自分にとって本当に必要か?」と一度立ち止まれるかが分かれ道です。
💬 COBARU流|お金が貯まる“買い物のチェックリスト”
|
チェック項目 |
質問 |
結果 |
|---|---|---|
|
使用頻度 |
週1以上使う? |
✅ Yesなら購入OK |
|
代替可能性 |
家に似たものはある? |
❌ Noなら買う価値あり |
|
買った瞬間ではなく、1週間後も嬉しい? |
✅ Yesで本当の満足 |
|
|
資産性 |
時間・学び・快適さを生む? |
✅ 成長投資ならOK |
この4つのうち3つ以上がYesなら、それは“浪費ではない支出”です。
💰 「節約」と「ケチ」は違う
節約は“選ぶ力”であり、ケチは“我慢の結果”。
違いはシンプルです。
-
節約 → 「使うべきところには使う」
-
ケチ → 「何がなんでも使わない」
たとえば、安い靴を3回買い替えるより、
高くても品質の良い靴を1足買う方がトータルコストは安くなる。
これが“コスパの真意”です。
節約上手な人は、**安さより「長期的な価値」**を基準に判断しています。
🧩 「安さ」から「賢さ」へ — 節約の進化論
資産が2400万円を超えた今、
私が実感しているのは「節約とは生き方の哲学」だということです。
安いものを追うほど、視野は“目先”に狭まる。
本当にお金が貯まる人は、「今」ではなく「未来」に焦点を合わせているのです。
-
“安い”より“価値がある”を選ぶ
-
“セール”より“タイムパフォーマンス”を重視する
-
“支出を減らす”より“お金の流れを整える”
節約とは、我慢の積み重ねではなく、選択の洗練です。
✨ まとめ|「安いから買う」は節約ではない
|
観点 |
安いから買う人 |
賢く節約する人 |
|---|---|---|
|
判断軸 |
値段 |
価値・必要性 |
|
感情 |
損したくない |
納得して使う |
|
衝動的 |
計画的 |
|
|
心の状態 |
常に不安 |
常に安定 |
「安い」は短期的な快楽。
「納得」は長期的な幸福。
その違いを理解したとき、節約は“義務”から“教養”へと変わります。
💬 最後に
節約とは、「お金を使わないこと」ではなく「自分を大切にすること」。
“安いから買う”をやめて、“納得して選ぶ”を意識するだけで、
お金の流れも、人生の流れも変わります。
私自身、2400万円以上に資産を増やしたのは、
給料が上がったからではなく、「お金との付き合い方」を変えたからです。
今日からでも遅くありません。
“安さの罠”から抜け出し、“賢さの節約”を始めましょう。
 CobaruBlog《コバルブログ》
CobaruBlog《コバルブログ》