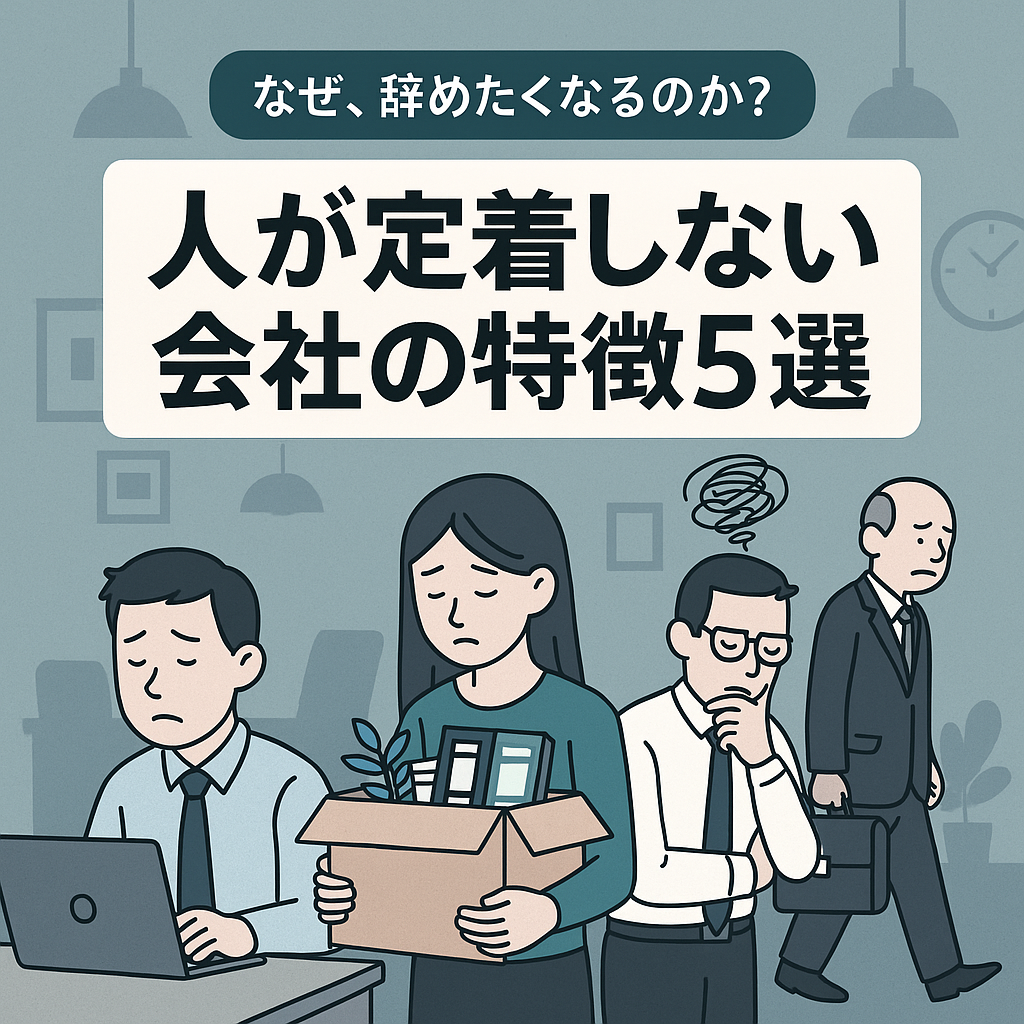🧐 なぜ「割高」と言われるのか簡単におさらい
まず、S&P 500が割高とされる根拠を確認しておきましょう:
- 過去10年以上の利益を平均化して評価する「CAPE(シラーP/E)」が、2000年のITバブル時以降で最高水準に達しています。
- 直近の予想P/E倍率など(フォワードP/E)が20倍前後と、歴史平均より高い水準にあります。
- こうした高評価のスタート点では、将来10年のリターンが低くなるという研究結果があります。
つまり、「今は株価がすでに高くなっているから、これから大きく上がる余地は少ないかもしれない」という見方ができます。
✅ それでも積立投資を続けるべき理由
では、なぜ評価が高い中でも積立投資(ドルコスト平均法+長期保有)が有効とされるのか、以下のエビデンスから見ていきましょう。
1. 高値でも長期ではリターンが出てきた実績がある
- たとえ「市場が高値」にあっても、長期(10年以上)保有できるなら、株式は成長しやすいというデータがあります。例えば、1950年以降で新たな最高値(オール タイム ハイ)で買った場合でも、「10年後に値下がりしていた事例は記録がない」という分析があります。
- また、1928年〜現在でのS&P 500の平均実質(インフレ調整)年率リターンはおよそ6〜7%とされています。 → 評価が高くても、“長く持てば”市場平均的な成長を享受できる可能性があるのです。
2. タイミングを狙うのは極めて難しい
- 「今は高いから待とう」とタイミングを図る人がいますが、研究では “高値で買う”=必ず損ではない という結果があります。RBC Global Asset Managementは「1950〜2023年でS&P 500が最高値にあった際に投資しても、1年・2年・3年後のリターンはほぼ市場平均レベルであった」と報告しています。
- 要するに、どこが「天井」かを正確に予想するのはほぼ不可能で、むしろ “市場に居続ける”ほうが勝ちやすいという結論です。
3. 仕組み(積立+分散+長期保有)が強み
高評価の市場だからこそ、次のような「仕組み」が投資成功のカギになります:
- 積立投資(ドルコスト平均法):定期的に一定額を買うことで、価格が高い時も低い時も買い続けられる。
- 長期保有:時間を味方にできれば、割高でも収益が積み上がる。
- 分散投資:高評価の米国株だけに偏らず、世界株式・債券・REITなども組み込むことで、リスクを下げられます。
実証研究でも、「スタート時点の評価が高いほどリターンは低く出やすいが、それでも長期保有+分散で平均以上の成績を出している」データがあります。
4. 割高=「上がらない」ではなく「上がりにくい」だけ
高い評価が出ているということは、これから「大きく上昇する可能性」が低いという意味合いではありますが、「下がる確定」という意味ではありません。
たとえば、S&P 500が“高値”水準にあっても、過去にはその後10年でプラスリターンを出してきた例も多数あります。
そのため、「割高」であることを理由に投資をやめてしまうのは、むしろ機会を失うリスクになるという研究報告もあります。
📌 実践すべきポイント(初心者向け)
割高でも積立を続けるなら、次のポイントを押さえましょう:
- 毎月・毎年、一定額を淡々と買い続ける。
- 「いつ買うか」ではなく「どれだけ長く持つか」を意識する。
- 資産配分を定期的に見直す。米国株中心でも、世界株式・債券・その他資産も。
- 評価が高いと予想される場合は、期待リターンを控えめに設定(例えば「年平均5〜6%」など)しておく。
- リスクが明らかな時期(例:値動きが激しい、景気後退が懸念される)でも、投資を止めずに継続するメンタルが重要。
🧾 まとめ
- S&P 500のような主要株式指数は、現在「割高」と言える指標があります。
- しかし「割高だから投資を止める」という判断は、長期観点からすると有効ではないというエビデンスが揃っています。
- 高評価でも、積立・分散・長期保有という仕組みを守ることで、将来の成長恩恵を取りに行く道があります。
- 特に初心者の方は、「完璧なタイミングを狙う」よりも「コツコツ続ける」ことの方が結果を左右します。
投資はマラソンです。スタート地点が「割高」かどうかよりも、 “走り続けられる準備” が整っているかが最も重要なのです。
 CobaruBlog《コバルブログ》
CobaruBlog《コバルブログ》